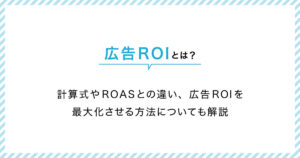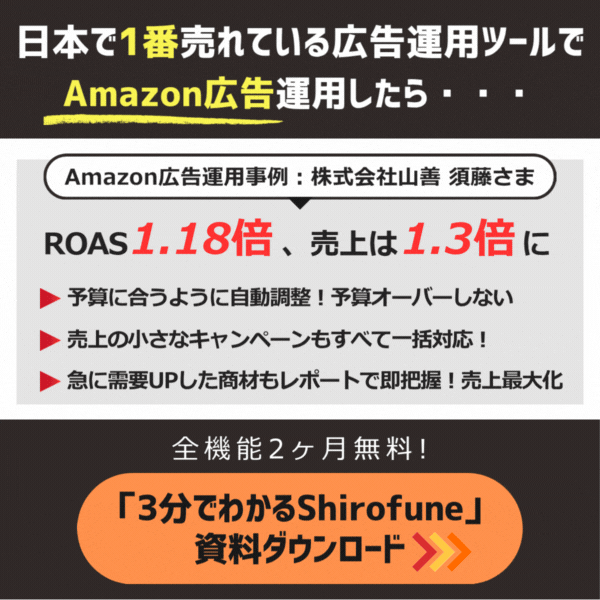広告ROIの目安や業界平均値から広告予算設定や戦略立案のステップを解説

- 戸栗 頌平
2025年のクリエイティブサーベイ株式会社の調査では、約85%の企業がマーケティング投資に対するコスト意識が高まったと回答する一方で、十分な予算がある企業はわずか18.8%にとどまりました。
こうした中で企業が利益につなげるには、広告ROIの追跡が欠かせません。しかし、WACUL株式会社の調査によると、広告ROIを重視している担当者は全体の25%にすぎず、広告運用においてROIは十分に活用されていないのが現状です。
その理由のひとつは、ROIの正確な測定が難しい点にあります。特にBtoBやSaaS、定期購入型などの事業では、初回CVだけでROIを評価しても実態を反映しません。とはいえ、ROIを見ずにクリック率やインプレッション数といった表面的なKPIばかりを追い続けると、成果を生まないまま予算を消化してしまうリスクがあります。
本記事では、広告ROIの基礎、目安、業界平均、そしてROIを軸にした戦略立案の考え方を解説します。
広告ROIの定義と計算方法の振り返り
まずはあらためて、広告ROIの定義と計算方法の振り返りをしましょう。
広告ROIの定義
広告ROIとは、広告施策に投じた費用に対して、どれだけの収益または成果を得られたかを示す指標です。そもそもROI(Return on Investment:アールオーアイ)とは投資対効果を意味し、投入したコストに対して得られる利益の割合を、数値で把握するために用いられます。
ウェブ広告の定番KPIとしては、ROAS(広告費用対売上高)がよく用いられます。ただし、ROASは「売上げ」に基づく指標であるため、数値が高く見えても、必ずしも事業の利益向上に直結しているとは限りません。
たとえば、BtoBやSaaSなど検討期間が長く、商材単価も高いビジネスモデルでは、短期的にはROASが低くとも、中長期的なLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を考慮すれば十分に成果が見込めるケースがあります。このようなモデルでは、ROASだけでは真のパフォーマンスを把握しきれないため、広告ROIの測定が不可欠となるのです。
さらに、広告ROIを定期的に測定することで、広告予算の最適な配分も可能になります。たとえば、限られた広告予算の中でリスティング広告、SNS広告、ディスプレイ広告など複数のチャネルを並行して運用している場合、どの媒体が最も高い成果を生んでいるのかを判断するうえで、ROIの比較は欠かせない指標です。
広告ROIの計算式
広告ROI(%)は、基本的に次の式で算出します。

ここでの「利益」とは、たとえばECでは「売上げ − 原価」で単純に算出できます。一方、BtoBのように売上化まで時間がかかる場合は、受注数やSQL(Sales Qualified Lead)などの中間指標を用いてROIを見積もるのが一般的です。
また、広告費には純広告費だけでなく、運用代行費、ツール費、LP制作費など関連コストも含めて計算します。利益がコストを上回ればROIはプラスとなり、施策が成果を上げたと判断できます。逆にマイナスであれば、コストが利益を上回っていることになり、早急にクリエイティブやターゲティングなどの見直しが必要です。
ROIは、ROASやCPAと組み合わせて分析することで、施策の精度をより的確に把握できます。特に、ROASが「売上げ」を基準にするのに対し、ROIは「利益率」を基準にするため、より本質的な評価が可能です。
広告ROIの目安や業界平均値をデータともとに紹介
ROIという指標は単体で見てもその良し悪しを判断するのが難しく、特定の基準と比較をしなければいけません。では、広告ROIの適正値はどの程度なのでしょうか。実際のデータや業界別の平均を紐解きながら、その実態を探っていきましょう。
広告ROIの目安や適正値の基準
広告ROIには絶対的な正解は存在しません。なぜなら、ROIは広告チャネル、商材の特性、ファネルの段階、ターゲットの温度感、さらに評価期間によって大きく変動する指標だからです。
たとえば、顕在層を対象としたリターゲティング広告ではROIが高くなりやすい一方で、潜在層に向けたディスプレイ広告や動画広告はROIが一時的に低く見える傾向があります。しかし、これを単なる失敗と捉えるのは早計です。これらの施策は、LTVを高めるための中長期的な布石となるケースが多くあります。
このように、前提条件を理解せずに業界平均や目安値と比較することは、誤った判断や戦略のブレを引き起こしかねません。一般的にはROI200%以上であれば良好とされることが多いものの、この数値はあくまで参考値であり、自社にそのまま当てはめるべきではありません。
たとえば、ROIが300%であっても、粗利率が30%しかなければ利益は出ず、逆に赤字となる場合もあります。ROIの高さだけを追うのではなく、そのROIが収益性を確保するラインを超えているかを見る必要があります。
適正なROIの判断基準としては、過去の実績、広告チャネル別・キャンペーン別のROI、さらにビジネスモデル上の損益構造をもとにした最低ラインの設定が有効です。平均値や他社事例を鵜呑みにせず、自社の状況に即した基準を持つことが、広告投資の健全化には欠かせません。
広告ROIの業界別平均のデータ
ここでは、実際の広告ROIの平均データを見ていきましょう。
Google広告の場合、2023年の全業界平均ROIは約800%であり、2024年にはGoogle自身のデータによると約200%に達すると報告されています 。ただし、これはリスティング広告を対象にしたものであり、ディスプレイ広告をはじめとした潜在層を狙った広告の場合は平均ROIが低くなる可能性が高いです。

この業界別ROIのデータは、広告に限らず企業全体の投資収益率を示しており、各業界における資本効率の違いを表しています。したがって、広告ROIの参考値として活用する際には注意が必要です。ただ、「自社の広告ROIが業界平均の資本ROIを上回っているかどうか」を見ることで、広告施策が他の経営資源投下と比べてどれほど有効なのかを判断するヒントになるでしょう。
たとえば、テクノロジー業界では全体の平均ROIが約17%であるのに対し、広告施策のROIが30%を超えていれば、広告投資が企業成長に大きく貢献している可能性があります。一方で、たとえCPAが低くとも、ROIが5%未満にとどまる場合、それは資源配分として非効率である可能性を示唆します。
また、これらの業界データは収益構造の違いを反映しており、単価の高い商材を持つBtoBやSaaS業界では、一件あたりのCVが売上げに与えるインパクトが大きく、ROIも高く出やすい傾向があります。逆に、低単価・大量販売型の小売や消費財では、ROIは売上規模に依存しやすく、広告以外の施策とのバランスがより重視される傾向にあります。
つまり、広告ROIを評価する際には、業界構造、商材単価、LTV、販売チャネルなど複数の要因を加味して、単なる数値の比較ではなく、構造的な納得感を伴う分析が必要です。ROIは数字であると同時に、経営視点で広告の価値を可視化する物差しでもあります。
広告ROIの目安や業界平均値を知ることがなぜ重要なのか
それでは、なぜ広告ROIの目安や業界平均値を知ることが重要なのでしょうか。ここでは、その理由を3つの観点から整理していきます。

目安を知ることで投資対効果の貢献度がわかるため
広告ROIの目安や業界平均を把握する目的のひとつは、自社の広告施策がビジネス全体にどれほど貢献しているかを客観的に評価することです。
ROIという数値が提示されていても、それが高いのか低いのか、優れているのかどうかは、比較対象がなければ判断できません。数値そのものの存在と、その意味を評価できることは別の問題であり、ROIは文脈に照らして初めて意味を持ちます。
たとえば、広告費として100万円を投下し、広告ROIが300%という結果が出た場合、広告活動によって得られた純粋な利益は300万円となり、一見して黒字と見なされがちです。しかし、同業他社が同じ投資でROI500%を実現しているとすれば、自社のパフォーマンスは見劣りします。このように、他社や業界水準との比較によって、はじめて自社の成果を的確に評価できるようになります。

加えて、ROIは広告に限らず、営業活動、人件費、販路開拓、システム開発など他の投資領域とも共通の軸で比較できる、数少ない経営指標です。広告費に100万円を投じるのと、別チャネルや施策に同額を投じるのとでは、どちらのリターンが高いのかを判断するためにも、ROIの目安は不可欠です。
精度の高い広告予算の設定や投資判断ができるため
広告費は「出した分だけ利益になる」と考えられがちですが、実際には投資効果が徐々に減る臨界点(限界効用逓減点)が存在します。この臨界点を見極めるには、同業界・同チャネル・同ファネル段階における他社の限界ROI、つまり目安や平均値を把握することが有効です。
たとえば、現在リターゲティング広告でROIが800%出ているとしましょう。
一見すると、「予算を増やせばさらに利益が出る」と思えるかもしれません。しかし、仮に業界平均が500%で、他社も拡張するにつれて500〜600%の範囲でROIが収束しているデータがあれば、現在の800%はごく一部の効率的な層にしか配信されていない可能性が高いといえるでしょう。このような状態で予算を拡大すると、ROIは低下し、非効率な投資に転じるリスクがあります。

つまり、目安や平均値を持たずに予算を拡大することは、効果の限界やリスクを把握しないまま投資判断を行うことであり、結果的に損失につながる可能性があります。
ROIの目安を持つことによって、予算設計には以下のような定量的判断が加えられます。
- このROI水準であれば、あといくらまで広告費を引き上げても利益を維持できる
- このキャンペーンのROIは業界平均を下回っているため、一時停止を検討すべき
- 現在のCPAでは利益が出る単価の上限を超えており、赤字リスクが高まっている
- 潜在層向け施策における低ROIが、戦略的に許容できるものか否かを見極められる
このように、ROIの基準が明確になれば、経験や勘に頼った属人的な運用から脱却し、事業全体の利益構造を前提とした投資判断が可能になります。
広告施策は、成果を積み上げるための手段であると同時に、損失を最小化する戦略でもあります。この視点に立てば、広告予算を設定する際に問うべきは「いくら投資するか」ではなく、「どこまで損失を許容できるか」であることが見えてくるのではないでしょうか。
あらかじめ目安や平均値を把握していれば、たとえ結果が期待を下回ったとしても、許容できる損失ラインを明確にしたうえで予算を投じる判断が可能になります。
他社と比べた自社のポジショニングがわかるため
企業活動の基本は、競合他社との競争において優位に立ち、市場シェアを拡大することにあります。そのためには、競合との比較によって自社のポジションを把握することが不可欠であり、広告ROIはその判断材料として有効です。
たとえば、ROIが300%だったとしても業界平均が600%であれば、その施策は十分な成果とはいえません。一方で、ROIが150%であっても平均が100%の場合は、相対的に高評価といえます。
重要なのは、自社がどの領域で優れており、どの領域で競合に遅れを取っているのかを正確に把握することです。この視点が欠けたまま広告施策を展開しても、戦略としての意味を持ちません。
業界平均と比較することで、得意分野や改善点を明確にし、そのうえでマーケティング全体の戦略を設計できます。「Facebook広告でROIが200%」「Google広告で500%」といった個別の数値だけで判断するのではなく、それらが競合と比べてどう位置づけられるのかまで踏み込まなければいけません。
広告施策の目的は単なる成果の獲得ではなく、市場における競争力の強化にあります。だからこそ、広告ROIの目安や業界水準を把握することが、戦略立案の第一歩となるのです。
広告ROIの目安や業界平均値と比較する際に考慮するポイント
広告ROIを業界平均や他社と比較する際には、いくつかの注意点があります。単純な数値の比較にとどまらず、広告の条件や目的、業界特性などを丁寧に見極めなければ、誤った判断を導く危険性があるからです。
ここでは、ROIを正しく比較・解釈するために押さえるべき3つのポイントを紹介します。

広告の条件
広告ROIを他社や他施策と比較する際に、最初に確認すべきは、比較対象の前提条件がそろっているかどうかです。ROIは、配信チャネル、ターゲット層、掲載期間、訴求内容などの要素によって大きく変動します。これらの条件が異なるまま数値だけを比較しても、妥当な評価は下せません。
中でも最優先でそろえるべきは、広告の配信チャネルです。たとえば、Googleリスティング広告は指名検索や購買意欲の高いユーザーを対象としており、ROIが高く出やすい傾向があります。一方で、YouTube広告は認知拡大を主な目的として配信されることが多く、ROIは相対的に低くなるのが一般的です。
このように、配信チャネルの違いは、ターゲットが購買ファネルのどの段階にいるかという温度感の違いを意味します。したがってROIを比較する際は、配信チャネルまたはファネル段階を可能な限りそろえる必要があります。
次に考慮すべきは、ROIの評価期間です。SaaS型ビジネスのようにLTVの回収に1〜2年を要する場合、初月のROIが50%であっても、長期的には十分な投資対効果を得られることがあります。対照的に、D2C型のEC商材では、ROIが2週間以内に200%以上にならなければ、採算が合わないケースも珍しくありません。
このように、ROIの評価には「いつまでに何を回収するか」という時間軸の視点が不可欠です。仮に他社のROIが高く見えたとしても、それが長期的な評価に基づいている可能性もあるため、表面の数値だけで判断するのは危険です。
さらに、広告のクリエイティブや訴求ポイントの違いも、ROIに大きく影響を及ぼします。同じチャネル・同じ商品であっても、期間限定セールで訴求した広告と企業の信頼性を前面に出した広告では、CVRやLTVが異なるため、結果としてROIも大きく変わります。したがって、ROIを評価・比較する際には、どの訴求で得られた成果かという背景を正しく理解する必要があります。
なお、外部に公開されているベンチマークデータの多くは、配信条件やターゲット属性といった前提情報が明示されていないケースが少なくありません。そのため、こうしたデータを参考にする際には、出典の背景を読み解き、自社の状況と照らし合わせて慎重に判断する姿勢が求められます。
業界の特性やビジネスモデルの違い
同じ広告施策であっても、業界やビジネスモデルが異なれば、ROIの基準や評価軸は大きく変わります。
たとえば、同じMAツールを扱っていたとしても、中小企業向けとエンタープライズ向けでは、リードタイムや導入プロセス、意思決定の構造に大きな差があります。エンタープライズ向けの製品では、複数の関係者が意思決定に関与し、成約までに長期間を要するのが一般的です。このような構造では、短期的なROIは必然的に低くなる傾向があります。
また、商材の単価によってもROIの意味合いは大きく異なります。
数百円程度で購入できる日用品と年間契約で数百万円以上を要する法人向けサービスでは、同じROIの数値であっても、投資対効果のスケールやリスクの捉え方はまったく異なります。さらに、高単価商材ではLTVや契約継続率の影響が大きく、ROIを判断する際にも、より中長期的な視点が求められるでしょう。

したがって、他社とROIを比較する際には、表面的な数値ではなく、業種・業態、ターゲット企業の規模、商品単価、営業プロセスの長さといったビジネス構造の共通点を丁寧に確認する必要があります。異なる構造を持つビジネスを比較対象に選んでしまえば、誤った解釈や意思決定につながりかねません。
このように、業界特性やビジネスモデルの違いを理解したうえでデータを読み解くことで、はじめてROIの比較は意味のある分析となります。
広告施策の目的と整合性
広告施策と一口に言っても、狙うターゲット層や顧客ファネルのフェーズによって、その目的や成果の見え方は大きく異なります。
購買意欲が高い顕在層を対象としたリスティング広告やリターゲティング広告、中長期的なブランド認知を目的とするSNS広告、興味喚起を狙う動画広告など、施策ごとに果たすべき役割はさまざまです。そして、それぞれの役割が異なる以上、ROIの評価軸も当然変わらなければいけません。
主な施策分類は、以下の通りです。

このように、広告施策が中長期的な関係構築を目的とするのか、それとも短期的な成果獲得を狙うのかによって、目指すべきROIの水準や評価の観点は大きく異なります。
にもかかわらず、実務の現場では「ROIが低い=失敗」と短絡的に判断されるケースが少なくありません。これは、施策ごとに適切なKPI設定ができていないことを意味し、本来の目的達成度の評価をROIという一つの指標に委ねてしまっていることが原因です。ROIは強い数値的説得力を持つがゆえに、評価軸として過剰に依存されやすく、施策の本質を見誤る構造的な誤認を生むことがあります。
こうした評価の誤りが続くと、広告戦略は次第に短期回収偏重の悪循環に陥ります。典型的なパターンは以下の通りです。

このような流れは、ROIをすべての施策に共通するKPIと誤って位置づけた評価設計に端を発しています。本来、ROIは目的ごとに設定されたKGIに対する、ひとつの補助的な評価軸にすぎません。
したがって、広告施策は目的に応じて次のように指標を切り分け、適切な評価を行うことが求められます。
- 認知拡大:インプレッション数、ブランド検索数、ビューアブル率
- 興味喚起・検討促進:リード獲得数、エンゲージメント率、平均セッション時間
- 購買促進:CV数、CPA、ROAS、AOV(平均注文単価)
- アップセル・継続購買:リピート率、継続率、LTV/CAC比
このように、施策の目的ごとに評価指標を適切に設計しなければ、すべての施策が短期売上へのROI貢献だけで一律に評価されてしまいます。その結果、本来必要とされる中長期の育成施策が正当に評価されず、広告戦略全体が持続性を失うリスクを招くのです。
広告ROIの目安や業界平均値を参考にした広告予算や戦略の立案ステップ
では、ROIの基準値を活用しながら、どのような手順で広告施策を設計していけばよいのでしょうか。ここでは、6つのステップでその流れを明らかにしていきます。

目標設定と現状分析
広告出稿において最初に行うべきは、目的の明確化です。目的が曖昧なままでは、ROIが高いのか低いのかを判断できず、適切な予算設計も立てられません。たとえば、認知拡大が目的であればリーチ数を最大化する配分が必要であり、売上最大化が目的であればCPAやROASが主要指標となります。
このように目的を明確にしたうえで、広告ROIという指標を位置づけましょう。ROIは単なる数値ではなく、事業目標に対して広告がどの程度貢献しているかを測る基準です。そのため、KGIとKPIの関係性を整理し、広告の果たすべき役割を明らかにすることが必要です。
目的が定まったあとは、現状把握に進みます。Google広告、Meta広告、LINE広告など、各チャネルにおけるROI、CPA、CVR、CTRを確認し、目標との乖離を見極めます。このとき、表面的なROIだけを評価指標とするのは不十分です。CVRの低下、CPCの高騰、LTVの下落といった要因を分解し、パフォーマンスを構造的に捉える必要があります。
また、初期段階で設定する目標ROIは、理想値ではなく損益構造から逆算すべきです。たとえば、粗利1万円の商品でCPAが9000円の場合、ROIは110%です。これを許容できるかどうかは、ビジネスモデルや成長フェーズに応じて判断する必要があります。重要なのは、「何%を目指すか」ではなく、「損益分岐ラインがどこか」という視点です。目標と現状の差を正しく把握することで、広告戦略の方向性が明確になります。
業界ベンチマークと競合分析
広告ROIの目標設定や現状評価において、自社内の数値だけを基準に判断するのは不十分です。自社のROIが高いのか低いのかを正確に把握するには、業界全体の標準や競合他社との比較が欠かせません。
業界平均や外部データを参照することで、自社の立ち位置を客観的に評価できます。さらに、競合の広告動向を分析すれば、相対的な強み・弱みが明確になるでしょう。たとえば、使用媒体やクリエイティブ、LP構成、キーワード戦略、訴求内容などを比較することで、自社との違いが見えてきます。
仮に競合が顕在層向けの施策に集中し、自社が潜在層への認知施策を重視している場合、短期的なROIに差が出るのは当然です。その違いを理解せず、自社のROIだけを根拠に施策を否定するのは、戦略的意図を見誤る危険があります。
このように、業界水準や競合の施策と自社の位置づけを照らし合わせて判断する視点が、正しい広告戦略の設計には不可欠です。
効果的なターゲットセグメントの設定
広告運用において、ターゲティングはROIを左右する最重要要素のひとつです。どれほど優れたクリエイティブを制作しても、どれだけ多くの予算を投下しても、適切でない相手に広告が届いては、成果にはつながりません。
まず確認すべきは、ターゲットの温度感です。今すぐ購入を検討している顕在層か、あるいはまだ課題に気づいていない潜在層かによって、期待すべきROIの水準は大きく異なります。たとえば、顕在層向けの広告でROIが150%にとどまる場合、それは非効率といえるかもしれません。しかし、同じ150%でも潜在層に対する成果であれば、むしろ良好な結果と評価できます。このように、ROIはターゲットの心理的ステージを前提に読み解く必要があります。
ターゲットの定義を、年齢・性別・興味関心といったデモグラフィック情報のみに頼るのは不十分です。本来注目すべきは、購買行動の段階、情報収集のスピード、決裁権の有無、課題意識の深さといった、バイヤージャーニーに基づいた心理的セグメンテーションです。

特にBtoB領域では、複数の意思決定者が関与するため、情報収集担当者向けの認知広告と、決裁者向けの比較訴求では、同じ商材でもアプローチが大きく異なります。当然、期待されるROIの水準も変わります。
また、ROIが高いセグメントを見つけたからといって、そこに無制限に投資を拡大するのは得策ではありません。広告の効果は一定規模を超えると逓減する傾向があり、限界効用の視点を欠いた運用はROIの低下を招くおそれがあります。
重要なのは、ROIの高い領域に資源を集中するだけでなく、成果の再現性や成長余地を見極めながら、持続可能な予算配分を行う設計力です。単なる数字の最大化ではなく、ROIを軸とした戦略的なターゲティングが求められます。
広告クリエイティブおよびLPの戦略的最適化
ターゲットが明確に定まったあとは、広告ROIを左右する要素として、クリエイティブとLPの精度が問われます。ターゲット設定がどれほど正確であっても、その対象に対して的確な訴求や導線設計ができていなければ、CVRは向上せず、ROIの改善にもつながりません。
まず前提として理解すべきなのは、クリエイティブの見た目やデザイン性が、直接ROIを高めるわけではないということです。ROIに大きく影響するのは、ターゲットが抱える「悩み」「欲求」「比較ポイント」に対して、どれだけ的確に訴求できているかです。そのためには、CVに至るまでの説得のプロセスを段階的に設計し、ユーザーが心理的な抵抗を感じずに次のアクションへと進めるようにする必要があります。
広告文では、商品の機能や特徴を列挙するだけではなく、「なぜ今それが必要なのか」「他社製品とどう違うのか」「利用後にどのような変化があるのか」といった、前後の文脈を含んだストーリー設計を意識しましょう。これは特に中〜高価格帯の商品やサービスにおいて重要な観点です。
一方、LP改善においては、まず広告との一貫性を確保することが基本です。たとえば、特定の商品を訴求する広告をクリックしたユーザーが、関連性の薄いトップページに遷移してしまえば、離脱率が高まるのは当然です。実際、ニールセン社の調査では、ユーザーがページ訪問から10秒以内に有益な情報を得られない場合、高確率で離脱するという結果が示されています。

(出典:ニールセン社)
LP内でのROIに影響する要素としては、次のようなポイントが挙げられます。
- ファーストビューの納得感と引き込み力
- 本文での情報補強と論理展開
- CTAの配置や種類、提示のタイミング
- フォーム設計における心理的ハードルの軽減
ただし、これらの改善策を単一の指標で判断するのは危険です。たとえばCTRが高くても、購買に至らなければ意味がありません。逆にCVRが良好でも、LTVが低ければ、ROIはむしろ悪化する可能性があります。広告とLPの最適化とは、ROIを分解し、因果関係をもとに改善要因を明らかにする作業です。単なるA/Bテストの繰り返しでは、構造的な最適化には到達できません。
本質的な広告運用に求められるのは、ROIを結果として受け止めるのではなく、事前に設計することです。ユーザーが「理解 → 納得 → 行動」に至るまでのあらゆる摩擦を解消し、意図通りに成果を生み出す広告設計が、ROIの向上には不可欠です。
入札戦略・広告配信設定の最適化
ROIを安定的に高めていくには、運用者の勘や経験に頼るのではなく、広告配信プラットフォーム側の仕組みや最適化ロジックに沿った設計が求められます。
まず確認すべきは、入札の目的が自社の広告戦略と一致しているかどうかです。たとえば、Meta広告でリンククリック数最適化を選択しているにもかかわらず、コンバージョン数をKPIに設定している場合、目標と運用方法が一致していません。このようなケースでは、広告がクリックしやすいユーザーにばかり配信されている可能性が高く、CV最適化へ入札目的を切り替えない限り、ROIの改善は見込めません。
次に重要なのが、広告配信におけるオーディエンスサイズの設計です。
ターゲットセグメントが狭すぎると、広告の配信学習が進まず、効果が安定しにくくなります。逆に、オーディエンスが広すぎると、本来狙いたいユーザー層に届かず、無駄な広告費が発生するリスクがあります。ROIを最大化するには、最小限の無駄と最大限の学習効率の両立を意識したオーディエンス設計が欠かせません。
さらに、予算配分の調整も重要な視点です。
ROIが1,000%を超える広告グループがあったとしても、その配信規模が小さければ、事業への貢献は限定的でしょう。一方で、ROIが300%程度でも、広告費を多く投下できる安定した広告グループであれば、より大きなリターンが見込めます。したがって、ROIの数値そのものだけでなく、投資規模に対して効率が持続可能かどうかという視点で戦略を設計しましょう。
継続的な効果測定と迅速な改善
ROIは、広告運用の成果を判断するための重要な指標ですが、その数値の高低だけで成功・失敗を判断するのではなく、どの部分に改善の余地があるかを把握するために活用する必要があります。
たとえば、ROIが低下している場合には、その原因がどこにあるのかを正確に特定する体制が求められます。原因は、クリエイティブ、ターゲティング、配信時間帯、LPの設計、ファネル構造など、さまざまな要素に分かれています。それぞれを切り分けて確認し、必要な対策を迅速に講じることが重要です。
また、改善にかかるスピードも成果に直結します。クリエイティブの変更、訴求内容の調整、ターゲティングの再設定などを適切なタイミングで行うことによって、広告の効果は大きく変わります。ROI改善には、数値の変化に対して迅速に対応できる運用体制が不可欠です。
ROIは、仮説を立て、検証し、改善を繰り返す中で活用されるべき指標です。重要なのは、数値そのものではなく、継続的に改善していく運用の仕組みを整えることです。
広告ROIを高めた具体的な事例
ここでは、広告ROIを高めた具体的な事例を紹介します。
事例①:ターゲティング再設計と媒体選定でROI倍
Retro Kidsは、レトロスタイルのおもちゃや雑貨を扱うブランドです。これまでのSNS広告ではCPAが高く、ブランドの認知度も低いという課題を抱えていました。
この状況を改善するために、広告代理店はFacebook広告のターゲティングを見直し、既存顧客と類似した属性を持つユーザーを対象とす類似オーディエンスを導入しました。
加えて、商品点数の多さを活かすため、Googleリスティング広告ではなくGoogleショッピング広告を選択。これにより、購買意欲の高いユーザーへの接触を強化しました。さらに、ホリデーシーズンに合わせて広告出稿量を15%増やすことで、需要の高まる時期に合わせたスケーリングを行いました。
こうした施策の結果、CPAは31%削減され、Facebookでのリーチは51%拡大。ホリデーシーズンの売上げは前年同期比で200%以上伸びました。最終的なROASは4.27倍に達し、広告費を大きく上回る収益を確保しました。
この事例では、特定の媒体や商品に依存せず、「誰に・どこで・いつ・何を届けるか」という4つの要素を再構築したことが、ROI改善につながった要因といえます。
事例②:迅速にPDCAを回し、勝ちパターンを特定

(出典:株式会社オーネット)
結婚相手紹介サービスを展開する株式会社オーネットでは、会員獲得効率の改善を目的に、YouTube広告施策に取り組みました。初期段階ではテレビCM用に制作した動画をそのまま活用していましたが、YouTube広告における成果は限定的であり、プラットフォーム特性に合った動画クリエイティブの必要性が明確となりました。
そこで同社は、効果検証のスピードと獲得効率の両立を重視し、外部パートナーと連携してYouTube広告に最適化された動画の制作に着手。初回制作の動画は高い成果を上げ、その後1年以上にわたって安定して活用されるクリエイティブとなりました。
最も顕著な成果はCPAの削減です。テレビCM素材を流用していた初期と比較し、CPAは約50%改善。広告の費用対効果が向上したことで、社内にも「YouTube広告は有効な獲得チャネルである」という認識が浸透したとのことです。
事例③:LTVの可視化でROIの最大化を目指した広告運用へ

(出典:formrun)
株式会社ベーシックが展開するフォーム作成ツール「formrun」は、無料登録から有料プランへの移行を促すフリーミアム型SaaSです。リードの獲得がそのまま売上げにつながるとは限らない構造の中、同社は広告の評価指標を見直し、ROI最大化を軸とした広告運用へと方針を転換しました。
従来、広告運用はすべて代理店に委託し、CV数(無料登録数)を中心に評価していました。しかしその成果はあくまで表面的な数値に過ぎず、本質的な利益貢献を捉えきれていないという課題がありました。こうした課題を受けて、同社は広告運用を内製化。ツールの導入により、LTVを基準としたROI計測と自動最適化が可能な体制を構築しました。
これにより、「広告が実際にどれだけ利益を生んでいるか」が明確になり、評価軸はCV数から利益効率へと大きくシフトしました。
社内には、「無料登録数が減っても、LTVの高いユーザーが多く獲得できていればROIは高い」という認識が定着。これにより、これまで曖昧になりがちだったKPIの優先順位も明確となり、ROIを基軸に広告運用を最適化するという文化が根づいていきました。
まとめ
広告は単なるコストではなく、利益を生み出すための戦略的な投資です。その正当性を客観的に示す指標として、欠かせないのがROIです。ROASが売上ベースの指標であり、LTVが将来予測に基づくものであるのに対し、ROIは「いくらの利益を生んだか」を明確に示します。
ROIを活用すれば、広告だけでなく、営業、人材採用、プロダクト開発といった他部門の投資とも、同じ基準で比較することが可能になります。CPAやCTRなどの広告特有の指標だけでは、組織全体として広告の価値を正しく評価することは困難です。経営判断において重視されるのは、最終的に利益に直結する指標であるためです。
広告施策は、成果の再現性を高めるための取り組みであり、その実行力を支えるのがROIを構成する要素、たとえば粗利、CVR、CPCなどの構造的な理解です。これらの指標を把握せずに運用するのは、収益性を見ずに資金を投下するのと同じであり、効率的とはいえません。
ROIという判断軸を持たずに広告運用を行えば、より収益性の高い投資機会を逃し、時間と予算を浪費するリスクが高まります。感覚や経験だけに頼るのではなく、成果を数字で語る姿勢こそが、広告運用の本質であり、その中心にあるのがROIです。
豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。