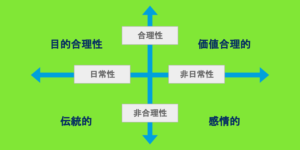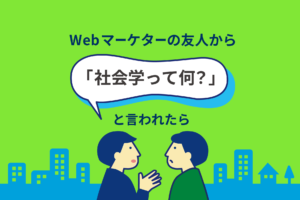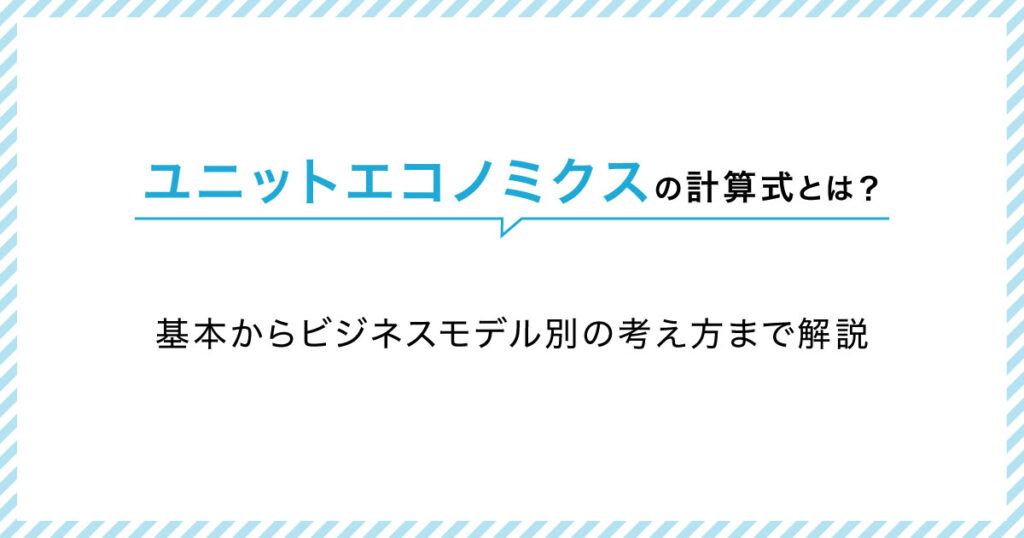
ユニットエコノミクスの計算式とは?基本からビジネスモデル別の考え方まで解説

- 菊池 満長
イギリスの経済紙「エコノミスト」は2025年以降の世界についての将来予測を発表しました。「アメリカの関税政策による貿易摩擦への懸念」や、「AIバブルはもうすぐ崩壊するのか?」といったトピックが盛り込まれるなど、経済やテクノロジーの動向を見渡すと不確実性、不安定性がますます増しているような印象を受けます。
このような社会の状況の中、事業を新規で起こすことや、今まで維持成長させてきたビジネスをこれからも守っていくためには、事業の健全性をいつでも客観的に評価し、その評価に基づいてアクションしていく体制が求められると考えられます。
そこで重要なのが「ユニットエコノミクス」です。本記事では、ユニットエコノミクスの基本や重要な理由、計算の仕方や、計算式の具体的な活用法などを紹介します。事業を評価する際のポイントや、改善の具体的なアプローチについても紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
ユニットエコノミクスとは
ユニットエコノミクスは、ビジネスモデルを構成する最小単位(例: 商品1個、サービス利用1回、顧客1人など)で収益性を分析する手法です。
特にスタートアップ業界ではこの考え方が重要視されており、多くの場合、顧客生涯価値(LTV=Life Time Value)と顧客獲得コスト(CAC=Customer Acquisition Cost)の比率によってその健全性が測られます。
SalesforceやHubSpotをはじめ、サブスクリプション型のBtoB SaaSのようなビジネスモデルが世界中で急成長を遂げ、BtoB・BtoC問わずさまざまな業界に浸透しました。このようなビジネスモデルにおいては、売上げの成長性は高い一方で、マーケティングや開発への先行投資が重く、短期的には決算上「利益が出ていない」「赤字が続く」といった具合に見えることも多くなります。
そこで、事業成長と投資構造について「1顧客あたりで本当に儲かっているのか?」「長期的には黒字になるのか?」というポイントを説明する必要が生まれ、そのためにユニットエコノミクスの考え方が重要視されるようになったのです。
この章では、ユニットエコノミクスの定義を詳しく解説するとともに、重要視される理由について掘り下げます。
ユニットエコノミクスの定義
ユニットエコノミクスは、ビジネスにおける「1ユニット」あたりの収益と費用を分析する手法です。ここでいう「ユニット」とは、ビジネスの性質によってさまざまに設定されます。
たとえば、製造業であれば製品1個、SaaS企業であれば顧客1人など、収益を生み出す最小単位が該当します。この最小単位ごとに得られる売上げと、それに要するコストを比較することで、事業が個々のユニットベースで利益を生み出しているかどうかを判断できるのです。
特にスタートアップの世界では、ユニットエコノミクスは顧客生涯価値(LTV)を顧客獲得コスト(CAC)で割った比率として定義されることが一般的で、このLTV/CAC比率がユニットエコノミクスの最も重要な指標となります。
たとえば、LTV/CAC比率が1:3である場合、「1人の顧客から生涯にわたって得られる収益が、その顧客を獲得するためにかかったコストの3倍である」ことを意味し、事業の健全性を示す重要なバロメーターとなります。
LTV(顧客生涯価値)とCAC(顧客獲得コスト)
LTVは、一人の顧客があなたの会社のビジネスと関わり始めてから関係が終わるまでの間にもたらす累積の売上げ(あるいは利益)の総額を示します。簡単にいうと、「ある顧客がその生涯で支払ってくれるお金の合計」と捉えられます。顧客が長くサービスを利用してくれたり、購入する金額が大きかったりするほど、LTVは高くなっていきます。
一方でCACは、一人の顧客を新規で獲得するために費やしたマーケティング費用や営業コストの合計です。具体的には、広告費、営業担当者の人件費、成功報酬など、顧客獲得に直接関係するあらゆる費用が含まれます。このCACは低ければ低いほど、効率的に顧客を獲得できていることを意味します。
なお、LTVに関しては別記事『LTV(顧客生涯価値)とは?言葉の定義や意味、計算方法や向上施策についてわかりやすく解説 』でより詳しく述べていますので、あわせてお読みください。
ユニットエコノミクスが重視される背景
近年、スタートアップを取り巻く資金調達環境は大きく変化しました。
以前は「成長最優先」という考え方が主流でしたが、現在は「収益性と効率性」を重視する傾向にシフトしています。実際、2023年には世界のスタートアップ投資が5年ぶりの低水準に落ち込みました。このような厳しい資金環境下において、多くの企業が支出を抑えることを強く意識し、ユニットエコノミクスの改善に注力していると報じられています。
市場が不安定な状況では、1顧客あたりで着実に利益を出せる、堅実なビジネスモデルがこれまで以上に求められているためです。
かつて、WeWork(コワーキングスペース運営)やUber(配車・宅配サービス)のような一部のユニコーン企業は、巨額のベンチャー資金を投じることで急成長を遂げました。ところがその一方、個々の取引では赤字を出し続けるという不健全なユニットエコノミクスに陥り、結果として市場の信頼を失うこととなりました。
特にWeWorkはIPOが目前に迫る中で、内部の経済性の悪さが露呈し、「ユニットエコノミクスの観点から高い評価を得られなかった」と指摘されています。
このような事例から、ユニットエコノミクスが不健全な状態で顧客数を拡大しても、損失が膨らむばかりで持続的な成長にはつながらないという認識が広まりました。そのため、早期からユニットエコノミクスを健全化することが、ビジネスの持続的な成長には不可欠であると強く認識されるようになったのです。
なお、より詳細は別記事「ユニットエコノミクスとは」で解説しているので、そちらもあわせてお読みください。
ユニットエコノミクスの計算式
ここでは、ユニットエコノミクスにおける最も要の計算式に焦点を絞り込んで紹介します。
ユニットエコノミクスの基本計算式
ユニットエコノミクスの基本計算式として、まずは以下を押さえましょう。
| LTV÷CAC>3 |
この計算式は、LTVとCACのバランス(比率)を算出してビジネスの健全性を評価することが目的です。LTVをCACで割った結果、3より大きければビジネスは健全であると判断できます。
「3より大きければ健全」と評価できる理由は、「マーケティング費用ほか諸経費を利益で十分にカバーできていて、さらにスケールが見込める」と考えられるためです。なお、LTVとCACの算出方法についてはこのあと解説します。
さらに詳しい内容は別記事「ユニットエコノミクスとは」で掘り下げて解説しているので、そちらもご一読ください。
LTV(顧客生涯価値)の算出方法
LTVは次の計算式で大まかに算出できます。
| LTV=(1顧客当たりの平均購入額)×(平均購入回数)×(平均継続期間) |
たとえば「顧客の平均購入単価が1万円、半年に1回購入し、顧客としての存続期間が5年」であれば、LTVは「1万円 × 年2回 × 5年 = 10万円」と算出できます。このように購入単価・頻度・継続期間の3要素を掛け合わせるのが基本的なLTV算出方法です。
また、BtoB SaaSなどのサブスクリプション型サービスなどでは、以下の計算式がよく用いられます。
| LTV=平均月次売上(ARPU)×粗利益率×平均契約期間(月数) |
たとえば「月額課金のソフトウェアで1ユーザーあたり月収益5000円、粗利80%、平均利用継続24カ月」であれば、「5000円 × 0.8 × 24カ月 = 9万6000円」がLTVとなります。
このように、事業特性に応じて計算式は多少異なりますが、いずれも顧客がもたらす累計収益の現在価値を求める点では共通しています。
なお注意点として、サブスクリプション型のビジネスモデルにおいては顧客の解約率(チャーンレート)や将来の収益の割引も考慮する必要があります。特に創業初期は十分な実績データがなく、解約率を楽観的に見積もってしまうケースが多いため、得られたLTVはあくまで仮説の値である点に注意が必要です。
また、可能であれば顧客ごとの粗利益ベースで計算する(原価や変動費を差し引く)ことで、より実態に近いLTVを把握できるでしょう。
さらに詳しくは「LTVの計算方法とは?算出する目的や具体的な求め方について具体例を交えて解説」で紹介していますので、そちらもあわせてお読みください。
CAC(顧客獲得コスト)の算出方法
CACは「特定期間に投下した営業・マーケティングコストの合計」を「その期間に獲得した新規顧客数」で割ることで算出します。
たとえば、1カ月間にマーケティング費用と営業人件費などで合計100万円を投下し、その月に100人の新規顧客を獲得できた場合、「CAC = 100万円 ÷ 100人 = 1万円/人」となります。基本的には、顧客一人当たりの平均獲得コストとしてシンプルに計算されます。
なお、CAC算出時には、単に広告費用だけでなく営業担当者の人件費やマーケティング部門の人件費、ツール利用料など「顧客獲得のために要したあらゆるコスト」を含める必要があります。しばしば広告費のみがCACだと誤認するケースもありますが、それでは実態より低く見積もってしまうこととなります。
また、無料チャネル(オーガニック流入)と有料チャネルを混同すると平均CACが不正確になるため、分析上は両者を分けて算出することも重要です。
マーケティング費用を投下してから顧客獲得に至るまでタイムラグがある場合には、費用と獲得数の対応期間を合わせる工夫も必要です。たとえば、前月の広告費で今月獲得した顧客が多い場合、そのずれを考慮しなければCACを過小評価・過大評価する原因になります。
顧客セグメントや市場、製品ラインごとなどで CAC を細分化して把握するなどの工夫など、適切な期間での集計と、チャネルごとのCAC把握によって、より正確なコスト評価が可能になるでしょう。
ビジネスモデル別:ユニットエコノミクスの計算と考え方
ユニットエコノミクスの計算(計算式の中で用いる指標)および考え方は、ビジネスモデルによって少しずつ異なります。ここでは、以下3類型に絞ってご紹介します。
- サブスクリプション型ビジネス
- ECビジネス
- 金融ビジネス
サブスク型ビジネスの場合
サブスクリプションモデルでは、本記事の前半でも紹介した以下の計算式を用いて事業収益性を評価します。
| LTV÷CAC>3 |
多くのベンチャーキャピタルやアナリストがLTV/CAC ≒ 3:1を健全な目安としています。実際、SaaSなどの継続収益モデルでは「CACの回収はLTVの約1/3以内」が望ましく、著名VCの分析でも「LTVはCACの3倍程度(公開上場企業では5倍超も)あること」が持続可能なモデルの条件とされています。またCAC回収期間も重要で、一般的に顧客獲得コストは12カ月以内に回収することが推奨されています。
また、サブスクリプション型ビジネスでは解約率(チャーン率)が直接LTVに影響します。たとえば月次解約率が2.5%なら平均顧客寿命は40カ月(1÷0.025=40)程度となります。「平均顧客寿命=1/チャーン率」で算出可能です。解約率をできるだけ下げて継続利用期間を延ばすことがLTV向上の鍵となるため、顧客維持(リテンション)施策がユニットエコノミクス改善に直結するといえます。
サブスクリプション型ビジネスでは1顧客あたりの単価が低い場合も多いですが、それでもLTV算出時には売上高ではなく粗利ベースで評価することが重要です。顧客から得られる累積利益とCACを比較することで、真の採算ラインを把握できるためです。たとえば、SaaSビジネスでは「年間顧客貢献利益(粗利)×平均契約年数」でLTVを計算し、CACと比較して収支バランスを確認します。
ECビジネスの場合
EC(物販)ビジネスではユニットエコノミクスを1回の注文(取引)または1人の顧客単位で考えます。
顧客単位で見る場合、「平均注文額(客単価)×購入頻度×顧客継続期間」でLTVを概算できます。
たとえば「1回あたり5000円購入・年26回購入・顧客寿命7年」といった平均顧客像を想定した場合、LTVは5000円×26回×7年=約91万円です。このように平均客単価・購入頻度・継続年数を掛け合わせるシンプルなモデルでLTVを見積もります。
なお、ECでは製造原価や物流費用が発生するため、LTVは売上高ではなく商品原価や配送コストを差し引いた「貢献利益」で1注文・1顧客あたりの収益性を算出し、それをCACと比較して採算ラインを評価します。この「貢献利益」ベースの計算によって、実際の利益率を反映したユニットエコノミクスを把握できます。
ECビジネスにおいては、顧客のリピート率がユニットエコノミクス改善の鍵です。一般に新規顧客獲得は既存顧客維持の5倍のコストがかかるとされ(『1:5の法則』※参考:『実践!LTV最大化 (顧客の生涯価値を上げまくる!有名企業との25年間の取組で習得した生涯顧客の育て方)』〔齋藤 孝太、2024年〕)、既存顧客のロイヤルティ向上によるLTV拡大が収益性に大きく寄与します。
たとえば、メール会員顧客は非会員よりも年間支出額が高く、LTVも向上するケースも報告されており、ロイヤルティプログラムやパーソナライズによって購入頻度・単価を上げる施策が有効だと考えられるでしょう。
金融ビジネスの場合
融資やフィンテックなどの金融業では、1人の顧客から得られる生涯収益をユニットエコノミクスの基礎とします。たとえば融資ビジネスでは、「平均貸付額×顧客あたり累計貸付回数」がひとつのLTV指標となるでしょう。融資の場合には顧客に対する「平均貸付額」が企業の収益源と位置づけられるためです。
一方、クレジットカード会社の場合であれば「顧客の年間利用額×カード継続年数」、保険会社なら「契約者が支払う累計保険料」が相当します。これら金融商品のLTVには利息収入や手数料収入など継続的収益を合算する点も重要です。
金融ビジネスでは、顧客獲得後にも各種コストが発生するため、ユニットエコノミクス分析時にはすべてのコスト要因を含める必要があります。具体的には、資金調達コスト(調達金利)、信用リスクによる貸倒損失、審査・与信判断のコスト、顧客サービスや債権回収コスト、さらには規制遵守コストまで、ローン実行から完済に至る各段階の費用を考慮して1顧客あたりの純利益を算出します。
たとえば「貸付業者のユニット当たり利益 = 利息収入 – 資金コスト – デフォルト損失 – 業務コスト」と考えられ、これがCACを上回るかどうかが収益性の条件となります。
また、デジタル化によるCAC削減が大きな差を生むとも考えられます。たとえば新規口座開設コストは従来の銀行では1人あたり約$150かかるのに対し、デジタルバンク(フィンテック)では$30程度に抑えられるとの海外の分析があります。
これはオンラインを介した手続きの効率化によるもので、他にもデジタル融資フローの自動化により審査時間短縮やリスク管理コスト低減が可能になれば、1顧客あたりの利益を押し上げる要因となるでしょう。多くの金融サービス企業では収益率が低く利益確保が難しいため、わずかなコスト削減の積み重ねが重要だとも指摘されています。
実際、多くの貸金業者は収支均衡か低マージンで運営しているのが現状であり、ユニットエコノミクス改善のためにマーケティング施策の工夫(例:地域特化広告や顧客紹介)、融資プロセスの最適化、クロスセルによる収益拡大などさまざまなアプローチが求められます。
一人ひとりの顧客を「損しない範囲で獲得・維持できているか」どうかについて綿密に分析することで、金融ビジネスのユニットエコノミクスを健全に保つことができるのです。
ユニットエコノミクスの評価基準・目安
ユニットエコノミクス(LTV:CAC比)の値は大きいほど良いのは確かですが、現実的な目安があります。
一般的によくいわれるのは「LTV:CAC比 = 3:1(3倍)が理想」という基準であり、これは「1人の顧客獲得に1円かけて、3円の価値を生み出せていれば望ましい」という感覚です。この3:1という比率は、多くのSaaSスタートアップやサブスク企業で健全かつ持続的成長が可能なラインとして認識されています。
また、この水準であればCACの回収期間(ペイバック期間)が概ね1年以内に収まるケースが多く、キャッシュフロー面でも安定しやすくなるでしょう。実際、CACを12カ月以内に回収できることがSaaSビジネスではひとつの健全性指標とされています。
次表は、「LTV/CAC」に関する解釈を簡単にまとめたものです。
| LTV/CAC ≒ 1 | 損益分岐点 | 1をわずかに上回る程度(たとえば1.2や1.5など)の場合、新規顧客獲得コストをようやく回収できるかどうかのラインを意味する。 利益はわずかで、ビジネスとしては成長余力が小さい状態。 特に1未満の場合、獲得すればするほど損失になるため、早急な改善が必要。 |
| LTV/CAC ≒ 3 | 健全な水準の目安 | 多くの成功企業が目指すべき比率。 顧客一人あたり十分な利益が確保できており、かつ成長への再投資余力も生まれる状態。 この水準なら事業は持続可能であり、投資家からも高評価を得られると期待できる。 |
| LTV/CAC > 5 | 成長投資の余地あり | 5以上となると、一見非常に優秀だが、逆にマーケティング投資を控えすぎている可能性も。 高い利益率を出せているなら、もっと積極的に広告や営業に費用を投下して市場シェア拡大を図る余地があるとも考えられる。 「ユニットエコノミクスが高すぎる=良い状態とは一概に言えない」という指摘もあり、特にベンチャー企業では成長機会を逃していないか検証が必要。 |
ユニットエコノミクスの健全ラインはビジネスモデルによって若干異なる場合があります。たとえばBtoB企業では契約単価が高く営業コストも大きいため、CAC回収に12カ月以上かかることも珍しくありません。そのため、自社の業態における業界標準や競合他社の水準も踏まえて目標値を設定する取り組みも推奨されます。
ユニットエコノミクスの改善施策
ユニットエコノミクスが思わしくない場合でも、企業努力によってLTVを向上させたり、CACを低減させたりすることで状況を改善できます。ここでは、代表的な施策をまとめます。
LTVを向上させる施策
LTVを高めるための戦略として以下3つのアプローチが考えられます。
- 購買単価の向上
- 購買頻度の向上
- 継続期間の延長
まず購買単価を上げるには、顧客により多くの、あるいは、より高額な商品を購入してもらう工夫が必要です。たとえば、関連商品を一緒に勧める「クロスセル」や、上位モデルへの買い替えを促す「アップセル」が考えられます。また、ただ割引するのではなく、「バリューパック」としてお得なセットを提供することや、商品をまとめて購入してもらう「バンドル販売」も有効でしょう。
次に、購買頻度を高めるには、顧客に繰り返し購入・利用してもらうための働きかけが重要です。具体的には、決済が未完了の顧客にメールやプッシュ通知で「お買い忘れはありませんか?」とリマインドしたり、過去の購入履歴に基づいて個別の商品をお勧めしたりする「パーソナライズドマーケティング」が挙げられます。定期購入や、ポイントプログラムの導入なども、継続的な利用を促す一手段となるでしょう。
最後に、継続期間を延ばし、顧客との関係を長く維持するための取り組みも重要です。顧客がサービスに不満を感じて離反してしまわないよう、顧客体験を向上させ、解約要因をできる限り減らしましょう。顧客の成功を積極的に支援する「カスタマーサクセス」の強化や、ユーザー同士が助け合える「コミュニティの活用」も、顧客がサービスを長く使い続けるための大きな要素となります。
CACを下げる施策
CACを効率的に下げるためには、以下のポイントが重要です。
- マーケティングの無駄をなくし、ターゲットを絞り込む
- 購買意欲の高い見込み客を確実に獲得する
- 既存顧客を大切にし、その力を借りる
まず、マーケティング費用を最も顧客獲得に効果的な部分に集中させましょう。闇雲に広告を出すのではなく、アトリビューション分析を使ってどの広告が本当に効果があったのかを見極め、自社の製品価値に共感し、長期的な顧客になる可能性が高い層に狙いを定めて予算を投下します。これにより、一件あたりの顧客獲得にかかるコストを最小限に抑えられます。
次に、一度興味を示したものの購入に至らなかった見込み客を逃さないための施策も実行しましょう。たとえば、Webサイトを訪れたが購入しなかったユーザーに対し、割引クーポン付きの広告やメールで再度アプローチすることで、購入を促します。すでに高い購買意欲を持つ層への再アプローチであるため、CACの削減につながりやすいでしょう。
さらに、顧客維持による再獲得コスト削減も、CACを下げるために欠かせません。新規顧客を獲得するには、既存顧客を維持するよりもはるかに多くのコストがかかります。そのため、ロイヤルティプログラムやサブスクリプションモデル、充実したアフターサポートなどを通じて既存顧客を大切にし、継続的に利用してもらうことが重要です。
既存顧客による売上げが増えれば、新たな顧客を獲得するための費用を削減でき、結果的にCACが下がります。また、満足した既存顧客がクチコミで新規顧客を紹介してくれれば、マーケティング費用をかけずに顧客を獲得でき、大幅なCAC削減につながります。つまり「紹介制度・アフィリエイトの活用」も、既存顧客や外部パートナーの力を借りて効率的に新規顧客を獲得する手法のひとつです。
なお詳細は別記事「ユニットエコノミクスとは〜」でも解説しているので、そちらもあわせてお読みください。
まとめ
本記事ではユニットエコノミクスの基本をテーマに、重要視される背景や、まず覚えてほしい計算式、その活用方法、事業成長性の評価の仕方、改善のポイントなどを解説してきました。
記事前半でWe Work社の事例も紹介しましたが、社内でユニットエコノミクスをないがしろにしていると投資家や市場からの信頼を失い、事業が暗礁に乗り上げるといった大きなリスクも懸念されます。
事業を継続的に成長させていくためには、日頃からユニットエコノミクスについて基礎から適切に理解し、施策一つひとつの実行可否や有効性などを客観的に評価する体制が重要です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。本記事が貴社の事業運営の一助となれば幸いです。

大手ネット広告代理店に新卒で2006年に入社し、一貫して広告運用に従事。
緻密な広告運用をアルゴリズム化し、誰もが高い広告効果を得られるようShirofuneを2014年に立ち上げ。
2016年7月に国内No.1を獲得し、2022年までに国内シェア91%を獲得。
2023年から海外展開をスタートし、現在までに米大手EC企業や広告代理店への導入実績。
2025年3月に米国広告業界で最古かつ最大級の業界団体である全米広告主協会からMarketing Technology Innovator AwardsのGoldを受賞。