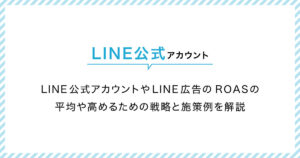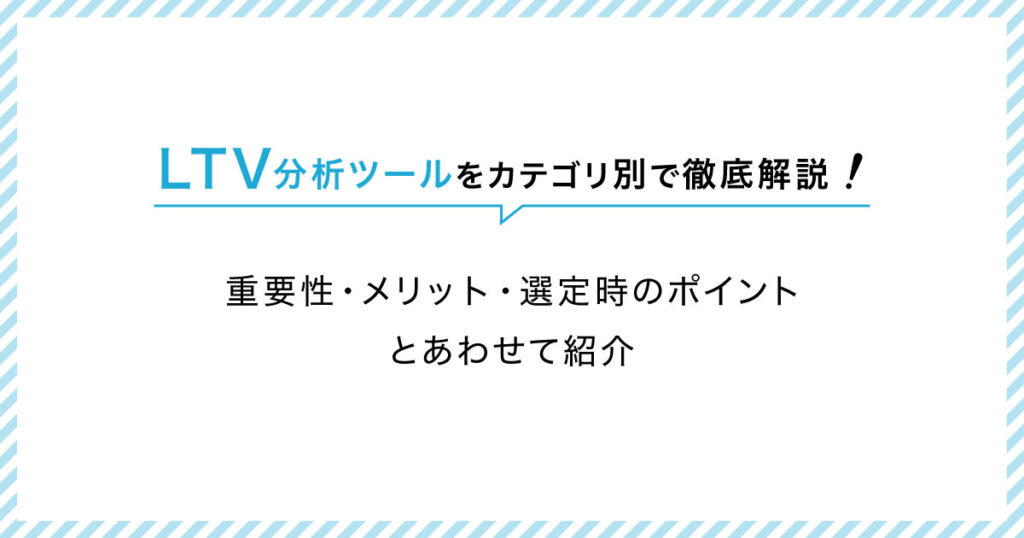
LTV分析ツールをカテゴリ別で徹底解説!重要性・メリット・選定時のポイントとあわせて紹介

- 戸栗 頌平
広告費の高騰による顧客獲得単価(CPA)の上昇、新規獲得偏重のメディア運用などのプレッシャーの中で「広告はとりあえずCVRとCTRを見ていればよい」という姿勢が、日本の広告運用の現場ではいまだに根強く残っています。
しかし、獲得した顧客が数カ月で離脱してしまうのであれば、そのクリックは結果的に赤字投資です。広告は本来、クリック後にどれだけ長期で価値を生み続けるか、すなわち顧客生涯価値(LTV)を伸ばす装置でなければなりません。
この視点は、クッキーベースのターゲティングに端を発する1990年代後半〜2000年代の「CTR至上主義」から、モバイルアプリ計測が発達した2010年代前半の「CVR/KPIマネジメント」を経て、ポストクッキー時代の現在、「ユニットエコノミクス(LTV/CAC)マネジメント」へと進化してきたAdtechの歴史そのものでもあります。
iOS14から追加された、App Tracking Transparency(ATT)と呼ばれるユーザーにクロスアプリトラッキングの許可を求める仕組みや、サードパーティクッキーの廃止が加速する中(SafariとFirefoxはすでにクッキー制限を実装し、プライバシー規制も強化。Chromeも2025年末までに廃止予定を表明し、全体のスケジュールが前倒しになっています。)、ファーストパーティデータに基づくLTVドリブンな広告運用は、代理店・事業会社ともに避けて通れないテーマです。
そこで本記事では、LTVを可視化・分析・活用するための最適なツールと選定ポイントを「数字で語る責任者」が納得できる深さで解説します。
LTV分析とは?
LTV分析とは、顧客が企業にもたらす総利益を定量化し、その構成要素を分解・改善するアプローチの総称です。MBAで頻繁に取り上げられる「バリューチェーン分析(企業の価値連鎖を工程ごとに分解し、価値とコストを評価する手法)」になぞらえれば、LTVは顧客ライフサイクル(獲得→オンボーディング→拡大→維持)の各工程で発生する利益を時系列で積み上げた“最終アウトプット”ともいえます。
そもそもLTVとは
LTV(顧客生涯価値:Life Time Value)とは、「一顧客との取引が始まってから完全に取引終了するまでに得られる総利益」です。
| “LTV(エルティーブイ)Life Time Value(ライフ・タイム・バリュー)の略。1人の顧客が取引を開始してから終了するまでの間にもたらす利益のこと。” (引用:インターネット広告基礎用語集(JIAA)) |
一顧客とはBtoBでは一般に一企業、BtoCでは1個人、1家族などです。LTVを出す計算式は複数ありますが、もっとも基本的な算出方法は以下です。
- LTV = 平均購入額 × 購入頻度 × 顧客継続期間
LTVは経営やマーケティング指標としてさまざまなシーンで活用されています。広告運用のシーンでは、ターゲティングや予算の最適化の指標として不可欠といっても過言ではありません。
なお、LTVには企業視点と顧客視点の2つの定義があり、LTV最大化のためには両視点を持つことが大切です。
- 企業視点:企業に対して、1人の顧客が一生涯でもたらしてくれる利益の合計額
- 顧客視点:顧客に対して、企業がもたらしてくれる価値の総量(経済的価値や満足度など)
(参考書籍:LTV(ライフタイムバリュー)の罠 のはじめに)
なお、LTVの考え方についてもっと詳しく知りたい方は、別記事「LTVとは」をあわせてお読みください。
なぜLTVを分析することが重要なのか
LTV分析は「将来の収益の可視化」「CXやサービスの改善」「解約率改善」そして「広告・営業活動の意思決定」に役立ちます。財務・顧客・内部プロセス・学習成長の4視点で戦略を可視化・管理するフレームワークであるバランスト・スコアカード(Robert S. Kaplan & David P. Norton, “The Balanced Scorecard—Measures that Drive Performance,” Harvard Business Review, 1992)に照らすと、次のような効果が期待できます。
- 「将来の収益」の可視化ができる(財務)
LTVは、現時点での顧客がもたらした収益ですが、そのデータをもとに顧客から得られる将来的な利益を予測できます。
たとえば3カ月前に加入した顧客のLTVは当然低い数値ですが、月々一定の料金が課金されるサブスクリプション型ビジネスモデルであれば、シンプルな計算式で1年後、2年後のLTVのシミュレーションが可能です。顧客の潜在的価値を評価できるため、たとえば広告運用シーンでも収益予測をもとに適切な投資ができます。
- 顧客体験設計やサービス改善の指針になる(顧客/内部プロセス)
LTVの高い顧客は、長期間にわたりサービスに価値を感じている顧客です。このような高LTV顧客の特徴や満足度が高い理由を知ることで、顧客体験設計やサービス改善へのヒントを得ることができます。
高LTV顧客の利用ジャーニーをRFM(Recency・Frequency・Monetaryの購買指標)×JTBD(顧客が「片付けたい用事」を捉える理論)で解析すれば、ロイヤル化の“勝ち筋”を発見できます。
- 解約率改善とのつながり(学習と成長)
LTVの低い顧客とLTVの高い顧客の共通点を比較することで、解約しやすい顧客層の特徴を把握できます。
低LTV顧客は一般に解約リスクが高いので、その共通行動をデシル分析(顧客を購買額順に10等分して特徴を把握する手法)によって明らかにすると、解約予兆となる行動が定量的に把握でき、CS施策を自動化できます。
- 広告・営業投資の意思決定に役立つ(財務/顧客)
LTV/CACとはユニットエコノミクスとも呼ばれる指標であり、事業の健全性や投資の指標として活用します。一般に、LTV/CPAが3以上あればビジネスは健全と判断されます(ビジネスモデルにより多少異なります)。
| LTV / CAC > 3 | 収益性が高く、ビジネスとして理想的 |
| LTV / CAC = 1.5〜3 | 成長可能な水準 |
| LTV / CAC < 1.5 | CACを下げるかLTVを高める必要がある |
営業部門もマーケティング部門も、最大の利益を達成するためには経費を適切にコントロールしなければなりませんが、その際に上記のLTV/CACの指標が判断材料となります。LTV/CAC>3を目標に、ターゲットCPAや入札上限を逆算。CTRの高いバナーでも、LTVが低ければ投資停止を合理的に説明できます。
LTVの可視化が難しいとされる理由とは
とはいえ、LTVを活用できている企業はまだ少数です。デジタル化を進める際のよくある課題ですが、「社内のデータ分散」「手動管理の難しさ」「人材リソースの不足」がネックになるからです。
理由1.顧客データが社内に分散している
一般に企業内にある顧客データは、EC、POS、CRM(顧客管理システム)、MA(マーケティングオートメーション)、Excelなど複数のシステムに分散されています。LTV算出にはデータを統合する必要がありますが、簡単ではありません。
特にオンライン・オフラインの統合には労力がかかります。オンラインのデータでもデータ形式が一致しないため、統合や分析に時間がかかることが少なくありません。顧客データの統合の段階で多くの企業が進まなくなります。
理由2.長期データの手動管理が大変
LTV分析のためには、顧客によっては5年、10、20年という長い期間の取引データが必要です。
しかし過去10年にわたる累積購買履歴を手作業で追うのは、非現実的といってよいほどの膨大な作業。そのため、顧客数が多く取引が長期にわたる企業ほど正確なLTVを出す難しさを感じ頓挫することがあります。
理由3.分析スキルや人的リソースの問題
手動でLTV分析するシステムを作る場合、RFM分析・コホート分析などの専門知識が必要です。また、LTVの計算には顧客の累積売上データだけでなく、顧客獲得コスト(CAC)、割引率、離脱率などの変数を考慮する必要があります。
そのようなスキルを持った人材が社内にいないと導入は難しく、仮にいる場合でも複雑な計算が必要なので、手動だとエラーが発生する可能性があります。
理由4.リアルタイム性・共有性の欠如
顧客データは日々変動します。手作業で集計していると直近の売上げやコストがリアルタイムに反映できません。
最新のデータが反映されていないLTVを指標にすると、最適な判断はむずかしくなるでしょう。また他部署と情報共有する際にもタイムラグが発生しがちです。
このようにLTV分析を手動で行うには課題が多いため、本格的にLTV分析をする場合はデータ分析ツールを活用することが一般的です。
LTV分析ツールを導入するメリット
LTV分析ツールを導入すると、「顧客データ統合」「優良顧客の発見」「解約予兆の検知・ナーチャリング」「広告・マーケ投資の判断」「レポート作成」が自動でできるため、業務が効率化されます。
メリット1.顧客データを統合し、LTVを可視化できる
社内にあるCRM、POS、広告プラットフォームなどに分散している顧客データを自動的に収集・統合できます。リアルタイムな顧客データにもとづいたLTVの可視化が可能になり、マーケティング業務の精度がアップします。
メリット2.セグメント分析による優良顧客を発見できる
セグメント分析により多様な切り口でLTVを算出できます。たとえば顧客を高LTV、中LTV、低LTVとグルーピングすることも可能です。高LTV顧客(ロイヤル顧客)にマーケティング予算を集中させることや、セグメントに最適化されたマーケティング施策を提供すれば、マーケティング成果の向上が期待できます。
メリット3.解約予兆の検知・ナーチャリング強化ができる
CRMデータをリアルタイムにとりこめるので、顧客データ(購買履歴、行動履歴など)をもとに解約兆候のある顧客を発見できます。早期にナーチャリングを強化したり、カスタマーサクセスと連携したりなど、解約を未然に防ぐ働きかけができます。
メリット4.広告・マーケ投資の最適化ができる
LTVは顧客の流入チャネル別に出すこともできます。各マーケティングチャネルのLTV平均をもとに、「CPA(Cost Per Acquisition:顧客獲得単価」)や「ROAS(Return On Advertising Spend:広告の費用対効果)」の許容値を設定すれば、マーケティング予算を適切に活用できるでしょう。
なお、ROASについてもっと詳しく知りたい方は、別記事「ROASとは」をあわせてお読みください。
メリット5.レポート自動化による業務効率化が実現できる
一般にレポートは上層部に見せることが多いため、作り込みに時間がかかるものですが、ツールなら短時間で作成可能。しかも常に最新データが反映されています。わかりやすく美しいレポートは誰もが理解しやすい点もメリットです。特定の分析スキルが高い担当者に依存することもないため、継続的にPDCAを回すことができます。
LTVツール選定時にチェックすべきポイント
ビジネスモデルによって最適なLTVツールは異なります。機能や価格だけでなく「活用の目的」「データ連携性」「サポート体制」などを運用視点で見極めることがポイントです。
ポイント1.自社のビジネスモデルに合った目的・KPIの整理
LTV分析ツールは、数値を算出するだけでなくLTVを最大化する目的で活用します。ツールを導入する前に、自社の業種や課題に応じた目標やKPIを明確にしましょう。
たとえば、EC型ビジネスならリピート率や単価、一定期間内の購入回数、Cart Abandonment Rate(カートに入れた商品の未購入率)などは、常に可視化したい指標です。サブスクリプションなら、MRR(月の定期収益)、CAC(顧客一人の獲得コスト)、ARPU(ユーザー一人あたりの平均月収益)、LTV:CAC(ユニットエコミクス)、Churn Rate(解約率)などが重要です。
ポイント2.連携できるデータソースの確認
これまでの顧客データが格納されているシステム(Shopify、Salesforce、Google広告など)と、スムーズに連携できるかどうかは重要ポイント。データ連携もしくはAPI連携、CDP(Customer Data Platform:カスタマー・データ・プラットフォーム)との連携可否などもチェックしましょう。
導入したのに既存システムと連携できないと、手作業でデータを移すことになり、自動化のメリットが大きく損なわれてしまいます。
ポイント3.コスト・日本語サポート・導入ハードルの確認
マーケティング成果が上がっても、システム費用が高すぎて収益を圧迫するようでは意味がありません。価格も大事です。チェックする際は、「初期費用」「月額費用」「最低契約期間」を必ず確認しましょう。海外ツールの場合、日本語マニュアルや導入支援の有無などのサポート面の確認も大切です。日本法人があるか、導入後の問い合わせ対応が可能かも判断基準です。
ポイント4.無料トライアルや導入支援の有無を確認
無料トライアルがあると、導入前に実際の画面や操作感を確認できます。オンボーディング時のサポートや運用サポートがあるかも必ずチェックしましょう。もしない場合、躓いた際に助けてもらうことができません。目的によっては導入後のコンサルティングの有無もポイントです。
カテゴリ別:代表的なLTV分析ツール
LTV分析ツールにはCRMツール型、MAツール型、EC特化型ツールがあります。12のツールを紹介しますので、自社のLTVツール選びの参考にしてください。
| LTVツールのタイプ | 向いている企業 | ツール名 |
| CRMツール型 | BtoB企業、顧客単価の高いビジネス、営業・CS組織がある企業 | Salesforce、HubSpot、 |
| MAツール型 | 見込み顧客が多い、キャンペーン施策を自動化したい中堅以上のEC・BtoB企業 | Adobe Marketo Engage、b→dash、SATORI |
| EC特化型ツール | D2C・自社EC運営企業、リピート通販、CRMに慣れていない中堅企業 | LTV-Lab、KARTE |
| カスタマーサクセスツール | SaaS/通信/サブスク型など、契約継続がLTVに直結するビジネス | CustomerCore |
| BI・分析ツール型 | 社内に分析人材がいて、既存のデータウェアハウス(DWH)を活用したい企業 | TableauLooker Studio |
CRMツール型(顧客管理・営業・CSと連動)
CRMツール型のLTV分析ツールは、BtoB企業、顧客単価の高いビジネス、営業部門やカスタマーサクセス部門など、顧客データを複数の部署が活用する企業に適しています。SFAやCSとの連携により、契約後のLTV向上施策にも活用できるからです。
Salesforce

(出典:Salesforce公式サイト)
提供企業: Salesforce, Inc.(米国)。世界を代表するSaaS企業のトップリーダー。
Salesforceは、高度なカスタマイズ性とデータ連携機能が強みのツール。SFA/CRMやサービスクラウドとの連携により、顧客ジャーニーにもとづいたさまざまな指標を可視化します。「顧客セグメント別のLTV比較」「解約リスク分析」など、多角的なLTV分析に役立つ指標が可視化できます。大手BtoB企業におすすめです。
サポート:日本語による複数チャネルのサポート、強力なコミュニティあり
HubSpot

(出典:HubSpot公式サイト)
提供企業: HubSpot, Inc.(米国)。インバウンドマーケティングを提唱したSaaS企業。
HubSpotは直感的で使いやすいインターフェースが特徴のツール。HubSpotも顧客取引データ、マーケティングクラウドのデータ、サービスクラウド、および連携できる外部ツール(1700種類以上あり)のデータをもとに、LTV向上に寄与するさまざまな指標を可視化します。広告運用に特化した無料ダッシュボードもあります。
また、設定や入力も比較的容易で、シンプルなレポート作成機能があるのもポイント。LTV向上に向けた施策の効果測定や改善を迅速に行えます。ITリテラシーがそれほど高くなくても導入・運用しやすいので、中小規模から成長中のBtoB企業に適しています。
サポート:日本語による複数チャネルサポート、豊富な教育コンテンツ他。
MAツール型(マーケ施策最適化・見込み顧客育成)
MAツール型は、顧客セグメント配信やスコアリング機能があり、LTVが高くなる可能性のある顧客の発掘育成ができます。シナリオ設定の自由度が高い点が既存のMA、CRM型ツールとは異なる点。見込み顧客が多く、マーケティングキャンペーンを自動化したいEC企業・BtoB企業に適しています。
Adobe Marketo Engage
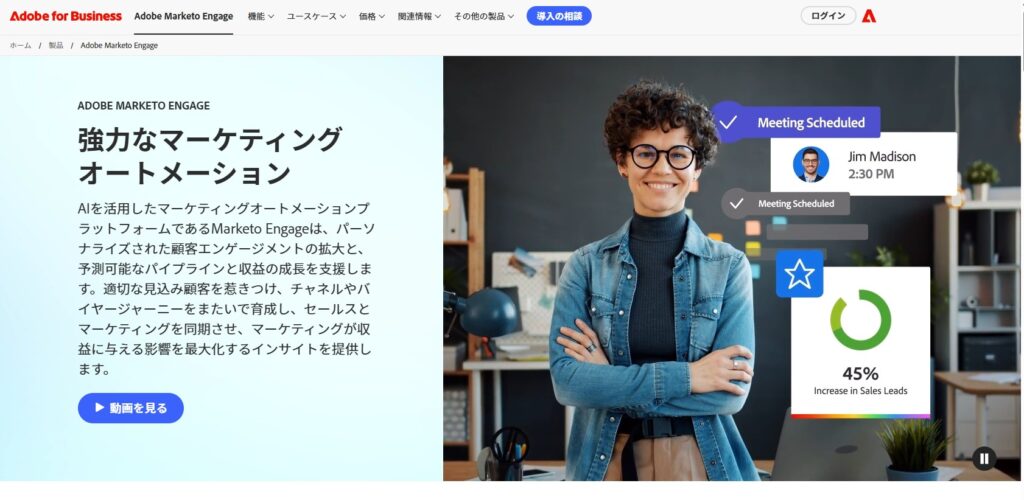
(出典:Adobe Marketo Engage公式サイト)
提供企業: Adobe Inc. (旧 Marketo, Inc.) 米国。クリエイティブソフトウェアで有名な企業ですが、エンタープライズ向けのデジタルマーケティングソリューションでも定評があります。
特徴: Marketo Engageは、高度なマーケティングオートメーションプラットフォームで、ターゲティングとOne to Oneコミュニケーションが強み。顧客データに基づき、多様なチャネルを横断したナーチャリング施策を展開し、エンゲージメントを高めることでLTV向上に貢献します。
サポート:日本語による複数チャネルサポートあり
b→dash

(出典:b→dash公式サイト)
提供企業: 株式会社データX(日本)。SaaSスタートアップ企業。
特徴:b→dashは、顧客行動データ、購買データ、広告データなどの多様なデータを統合し、AIによる高度なセグメント分析や予測分析ができるツール。LTV分析に役立つさまざまな指標が可視化できます。
最適なタイミングで顧客とのコミュニケーションを提示できるため、アップセル・クロスセル、離反防止に役立ち、結果的にLTVが向上することも期待できます。データドリブンなLTV向上を目指す企業に適したツールです。充実したオンボーディングプログラムなどサポート体制も整っています。
SATORI

(出典:SATORI公式サイト)
提供企業: SATORI株式会社(日本)。日本のスタートアップ企業。国産MAツール「SATORI」を開発。
特徴: SATORIは既存顧客や匿名顧客のWeb行動履歴を可視化し、興味関心に合わせた情報を提供することで、コンバージョンや案件化を促進するツールです。コンバージョンや案件化、成約を後押しするためLTV最大化に寄与します。インサイドセールスとの連携機能もあり、リードナーチャリングを強化したい企業に特に適したツールです。
サポート:導入から運用まで専任の担当者がサポート。
EC特化型ツール(購買履歴分析・リピート促進)
ECサイトに特化したLTV分析ツールです。RFM分析・継続率・広告チャネル別LTVなどがすぐわかるところが長所。D2C(メーカーの直販サイト)・ECサイト運営企業に適しています。検討時は、対応しているカート・決済サービス、CRMとの連携有無がポイントです。
LTV-Lab

(出典:LTV-Lab公式サイト)
提供企業: 株式会社SUPER STUDIO(日本)。SaaSスタートアップ企業
特徴:「LTV-Lab」は、EC上の顧客の行動データと顧客の購買頻度や購入金額を紐づけることで、顧客一人ひとりのLTVを正確に把握できます。「LTV向上分析」という機能でLTV分析、LTV推移などがリアルタイムにわかり、離反予測なども分析可能。初期設定が比較的簡単で、データ分析の専門知識がなくても扱えるため、中小〜中堅規模のEC企業やリピート通販企業に特に向いています。
サポート: 導入時の設定や初期導入のサポート、運用サポートあり。
KARTE

(出典:KARTE公式サイト)
提供企業: 株式会社プレイド(日本)。日本のCXプラットフォームプロバイダー。
特徴: KARTEは、ECサイト上の顧客ごとの行動・感情を可視化できるツールです。広告チャネルごとのユーザーのLTVをダッシュボードでリアルタイムに分析できるので、マーケティング施策や予算の最適化に役立ちます。UIもシンプルで見やすく初心者向きです。
サポート:導入時の目標設定から活用方法まで、カスタマーサクセスチームが伴奏サポートを提供。
カスタマーサクセスツール(チャーン予測・アップセル)
カスタマーサクセスツールとは、顧客のヘルススコア、解約予兆通知、担当者タスク提示など、CS業務のDX化が可能になるツールです。
CustomerCore

(出典:CustomerCore公式サイト)
提供企業: 株式会社Customer Core(日本)。SaaSスタートアップ企業。
特徴:CustomerCoreは、顧客の利用状況やエンゲージメントデータを可視化し、LTV最大化を支援するツールです。顧客のヘルススコアから離反リスクのある顧客を早期検知、アップセル・クロスセルの機会発見などのアクションを通じて、LTV向上に貢献します。
サポート:導入時の設定やオンボーディングプログラム、コンサルティングサービスあり
BI・分析ツール型(自由度重視・内製化志向)
BI・分析ツール型は、あらゆる社内データを使って、LTVを自社定義で深く掘り下げられるメリットがあります。社内にSQL等データ分析に関するスキルが高い人材がいるか、運用体制がある企業向きです。
Tableau
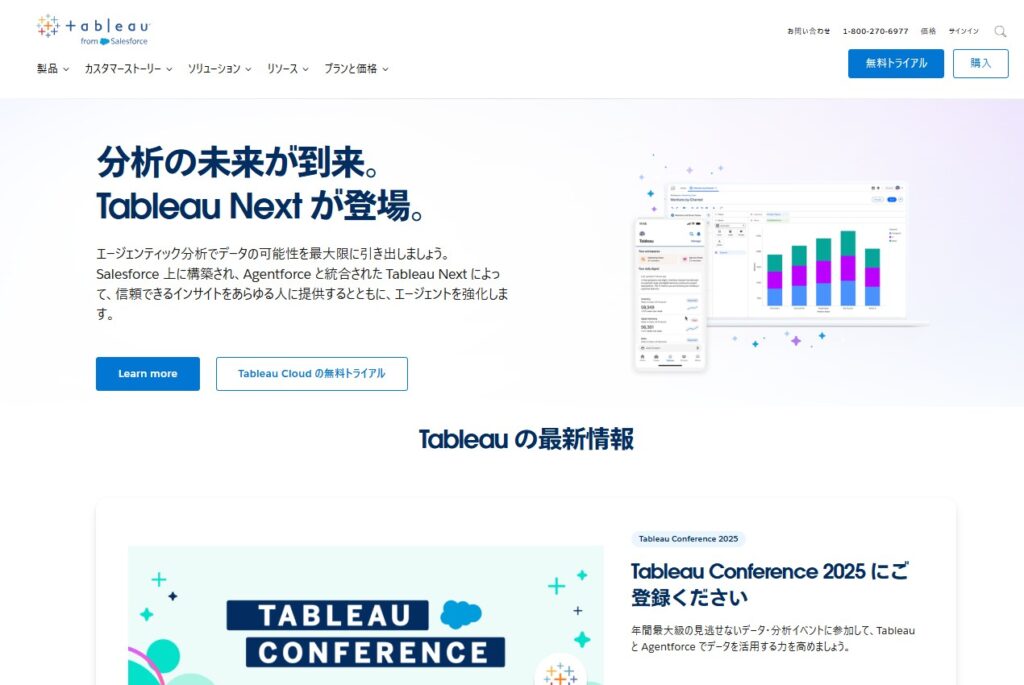
(出典:Tableau公式サイト)
提供企業: Salesforce, Inc. (米国:旧 Tableau Software, Inc) ※2019年にSalesforceに買収され現在はSalesforce参加
特徴:Tableauは、Excel、CSV、SQLデータベース、Hadoop、Salesforceなどの複数のデータソースと接続可能。LTV計算に必要なさまざまなデータをドラッグ&ドロップ操作で簡単に結びつけられるツールです。
最新の顧客行動を反映したLTV分析はもちろん、顧客の購買履歴や行動データを用いて、5年間のLTV予測やコホート分析のグラフ化も可能。顧客自身が多様な切り口でLTVを深掘りできるツールです。
サポート:日本語サポートあり(電話によるサポートはプランによる)。コンサルティング、トレーニングなどの有料サービスあり。
Looker Studio

(出典:Looker Studio公式サイト)
提供企業: Google LLC(米国)
特徴:GoogleアナリティクスやBigQueryなどの、Googleの他サービスと連携しデータを分析・可視化するBIツールです。800以上の外部のプラットフォームと接続可能であり、幅広いデータから多様な指標を分析できるうえに、レポートテンプレートも豊富です。Googleエコシステムを活用してLTV改善を目指したい企業向きです。
サポート: ヘルプセンターやコミュニティフォーラムは日本語対応。直接サポートはGoogle Workspaceのサポート範囲内で対応。FAQが充実。
まとめ
LTV分析は、「将来の収益の可視化」「CXやサービスの改善」「解約率改善」、そして「広告運用や営業活動の意思決定」に役立ちます。とはいえ、LTVの算出には企業内の多様なデータを結合させなければならず、膨大な手間暇がかかります。
近年は優れたLTV分析ツールが増えています。ツール導入によってリアルタイムにLTVが可視化できるようになればマーケティングROIも向上しますし、業務の属人化・判断ミスや遅れも解消できるでしょう。
まずは自社の課題と照らし合わせてツールのカテゴリを選定し、無料トライアルや相談を活用しながら検討を進めてみましょう。本記事が、みなさまの日々の業務に役立つことを願っております。
豪州ビジネス大学院国際ビジネス修士課程卒業。複数企業と起業を経てBtoB専業マーケティング代理店へ。その後、外資SaaSのユニコーン企業の日本法人立上げを行い、法人営業開始後マーケティング責任者として創業期を牽引。現在、日本のBtoBマーケティングの支援事業を行う株式会社LEAPTにて代表取締役。また、株式会社Shirofuneの外部マーケティング責任者を兼任。